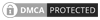京都には古い歴史があり、他所の地域にはない「しきたり(風習)」があります。京都を訪れた際は観光スポットを巡るのもいいですが、京都らしい独特の文化を探すのも、また違った発見があって楽しめると思います。そんな京都のしきたりを、いくつかご紹介しますね!
独特の風習が残る京都
http://blogs.yahoo.co.jp/hiropi1600/54246624.html
京都では昔から受け継がれている数々のならわしがあります。かつての都であり、文化や政治の中心地だった京都は、独特の風習が残っています。お互いに暗黙の了解で結ばれていることが多いのですが、他の地域の方からすると不思議に思えるかもしれません。京都ならではのこんな「しきたり」
祇園祭のときに胡瓜は食べない

http://stamp-collection.blog.so-net.ne.jp/archive/201209
祇園祭は八坂神社のお祭りで、7月1日から始まります。その八坂神社の家紋と胡瓜の断面が似ていることから、7月は胡瓜を食べないのです。胡瓜の断面と見比べてみましょう。なんとなく、似ているかも?

http://yasaichan.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_c70a.html
待ち合わせ時間よりもすこしだけ遅れる京都時間

http://blog.livedoor.jp/tokizoen/archives/51824439.html
京都では、訪問をする際には時間よりも少しだけ遅れるのがマナー。来訪の準備をしている先方のことを思いやる気持ちからです。とはいえ大幅に遅れるのではなく、髪の毛1本ほど遅れるのが京都のマナーです。髪の毛1本という表現が京都らしい表現ですね。黄白の水引を使う

http://www.mizuhikiya.com/shopping/shugi-butuzi.html
水引といえば慶事には紅白、仏事には黒白の水引を使います。これは御所と縁の深い京都ならではのならわしです。御所で慶事に使われる紅白の水引の色が濃く、黒く見えることからそれと区別するために黄白の水引を使います。黄色は黄泉の国をあらわす色とも言われています。目で見えるものにはどんなものがある?
屋根の上の鍾馗さん
http://blog.kyyyo.jp/2008/02/post-38.html
京都の町家の小屋根に「鍾馗さん(しょうきさん)」が祀られています。鍾馗さんは中国から魔よけとして伝わっています。京都のでも魔よけや家の守護として祀られています。鍾馗さんは決まったものはなく、色々なポーズ・表情をした多様な鍾馗さんをみることができます。鍾馗さんを探す時のコツですが、だいたいは下の写真のように1階の屋根の辺り(写真中央参照)に祀られています。町家を散策するときだけでなくバスに乗っているときにも探してみましょう。鍾馗さんを探しに京都に旅行に来る人もいるほど、意外な人気があるんですよ!

http://blog.livedoor.jp/rekishi_tanbou/archives/1683912.html
玄関に飾ってある粽

http://olaf-mama.at.webry.info/200908/article_12.html
粽といえば食べるものですが、京都では厄除けのお守りとして玄関に飾られています。この粽は祇園祭の各々の山鉾や八坂神社でも購入することができます。玄関の上に飾られている粽は町家だけでなく店舗などにも多いので探しやすいです。赤ちゃんの額に大、小の文字

http://kdesign.ldblog.jp/archives/51520478.html
生後30日くらいの赤ちゃんはお宮参りにいきます。京都ではお宮参りの時、男の子は「大」女の子は「小」の文字を額に書きます。これは男の子は強くおおらかに、女の子は優しく育つように願いが込められています。下鴨神社など大きな神社でお宮参りの際に見ることができます。台所に貼ってある「火迺要慎」の札

http://blog.livedoor.jp/rekishi_tanbou/archives/1783187.html
京都の町家やレストランの厨房などで「阿多古祀符 火迺要慎(あたごしふ ひのようじん)」と書かれたお札を見かけることがあります。これは京都の愛宕山のお札で「火迺要慎(ひのようじん)」=火の用心の御札です。京都の愛宕山では3歳までににお参りすると一生火難に遭わないと言われています。7月31日から8月1日に愛宕山に登ることを「千日詣り」といい千日分のご利益があるといわています。京都に行くと有名な神社仏閣や人気の観光地に目が向きますが、旅行のちょっとした合間の楽しみとしても知っておくと、さらに京都旅行が楽しくなりますよ!