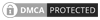昭和初期に建てられたという日本の気候・風土と日本人の暮らしに適った理想の住宅が、京都・大山崎に今も残っています。それが今回ご紹介する京都の穴場スポット「聴竹居」。
昭和初期に建てられたという日本の気候・風土と日本人の暮らしに適った理想の住宅が、京都・大山崎に今も残っています。それが今回ご紹介する京都の穴場スポット「聴竹居」。大山崎の緑の中にたたずむ洋風の瀟西な外観と、和風を基調とした内装のこの住宅は、住みやすさを追求した様々な工夫が見られ、和風の集大成といえる戦前の代表的木造建築物であり「すまいづくりのお手本」として多々紹介されています。
聴竹居とは?

http://blog.goo.ne.jp/doyasa1716/e/d1adbff0909e8e0455aba3c47767ed9c
京都府乙訓郡大山崎町の天王山の麓に創建時と変わらぬ姿で建つ「聴竹居」(ちょうちくきょ)は、建築家・藤井厚二(1888~1928)の第5回目の実験住宅(自邸)です。今から90年ほど前の昭和3(1928)年に作られた環境共生住宅の原点といわれる建物です。日本の近代建築20選の建物であり、藤井厚ニという大正から昭和にかけて活躍した建築家の建てた家です。
藤井厚二という人物
建築家藤井は1888年の生まれ。広島の経済的にも文化的にも恵まれた環境で育ち、東京帝国大学建築学科を卒業後、竹中工務店に勤め31歳のときに退社し、海外へ。やがて京都帝国大学の講師、助教授、そして教授となります。そして40歳で京都府大山崎の山手に1万坪もの土地を購入。この地でほぼ2年ごと計4回、自邸を建て、それを知人に譲り、また自邸を建てるということを繰り返し、これらの住宅に実際住むことにより日本の風土に適した住宅の在りようを追求しました。
1928年(昭和3年)に完成させた現存する最後の1棟は「聴竹居」と命名され、近代住宅建築の名作として名高いです。
聴竹居の魅力

http://blog.goo.ne.jp/doyasa1716/e/d1adbff0909e8e0455aba3c47767ed9c
「聴竹居」は日本最初の環境住宅であり、当時、西洋の影響を受けた建築物が乱立して、日本の建物の良さを忘れてしまっていることに危惧を抱いた建築家藤井厚二が、日本に相応しい和洋折衷の建物の建築を目指した住宅です。日本の数寄屋建築に見られる木材の巧みな使用、小さな凹凸を多用した空間、障子などの紙を使う採光の方法などを用い、木材家具による作りつけの凹凸空間(ちなみに藤井は作りつけの家具だけでなく、椅子、テーブル、照明器具に及ぶまで自作しています)、外光や電気の光を散光させるために用いられた天井や照明器具の薄美濃紙、網代天井なども魅力的です。
建物に見られる数々の工夫

http://blog.livedoor.jp/rekishi_tanbou/archives/1765533.html
「聴竹居」の魅力はその風情溢れる建物の雰囲気ももちろんですが、心地よい生活空間としての工夫も随所に感じられます。
「聴竹居」は真夏でも涼しく、真冬は木のぬくもりが感じられるように工夫されています。真夏に訪れてもどこか爽やかな空気に包まれている秘密は淀川から上がってくる西風を室内に取り込んでいるため。外の土台に風穴を開けて、中に通しているという仕組みがなされています。
屋根の軒先の角度を見事に調節することで、室内に入り込む日差しの量や角度も調整されていて、上部に刷りガラスを入れることにより外から軒先が見えないように細かい部分まで配慮されています。
女性や子供にも配慮した客室

http://blog.livedoor.jp/rakuentaniguchi/archives/51517245.html
大事なお客様が過ごす客室には、より一層、使う人の事を気遣った演出が見られます。客室に入ると自作の机と椅子が目に入ります。
椅子は着物を着た女性が座りやすいように座後ろを大きく開けてあります。また和と洋の空間でそれぞれ座った人同士の視線の高さが噛み合うように工夫されていて、目に見えないところにまで配慮がされています。お子様用の作り付け机がかわいらしく、愛情を感じますね。
ボランティアによるガイド
「聴竹居」は説明なしで、自由に見学してもいいそうですが、ボランティアさんに頼めば、建物についての詳細な説明を聞きながら見学する事が出来ます。好きなように見て回るのも楽しいですが、「聴竹居」の建てられた背景や建築家藤井厚二の意向など、「聴竹居」の魅力をより深くしることが出来るので、ぜひボランティアさんにガイドをお願いしてみてください!
見学の方法(予約制)
見学予約になります
見学希望日の3ヶ月前の1日(5月の見学の場合は2月1日)から見学希望日の2週間前のその曜日までに予約をします。予約方法
予約は先着順。次のメール([email protected])宛に、見学したい日と時間(第1~第3希望記入)、見学者全員の氏名、所属と、申し込み代表者及び連絡担当者の氏名、所属、住所・電話・FAX番号・メールアドレスを記入のうえ申込みます。見学時間
水曜日・金曜日・日曜日 10時~15時【1】10時~ 【2】11時~ 【3】12時~ 【4】13時~ 【5】14時~
見学資格
小学4年生以上限定です。18歳未満の学生・児童は先生もしくは保護者の付き添いが必要です。見学料
見学料:大人1000円 学生・児童(小学4年生以上)500円です。聴竹居を訪れた方の声
聴竹居すごくよかった。木造やっぱ好きだなあ pic.twitter.com/MLGS22R1pt
— かおり (@moipocoe) 2015, 7月 19大山崎の聴竹居に来ました。一般公開の日です。建物内部の見学は約1時間待ち。 pic.twitter.com/Ct6a0i9DG8
— 大谷敏幸 (@toshijump) 2015, 4月 29今日午前のまいまい京都、大山崎コースで見学した日本初のエコ住宅「聴竹居」。紅葉が綺麗でした。と言いつつ、撮った写真をただいま現像ちう! #まいまい京都 pic.twitter.com/COHflzN2OC
— ふくなが (@Photo_Le_Couple) 2013, 12月 8基本情報
■ 基本情報
- ・名称:聴竹居
- ・住所:京都府乙訓郡大山崎町大山崎谷田31
- ・アクセス:JR山崎駅、阪急大山崎駅から徒歩約10分~15分
- ・電話番号:080-6117-7510(荻野和雄様)
- ・公式サイトURL:http://www.chochikukyo.com/
一緒に見たい大山崎の観光スポット
http://blogs.yahoo.co.jp/momonakai/19059660.html
「聴竹居」のある京都・山崎は京都府の南西端に位置します。ちょうど大阪と京都の県境がある場所になります。
天王山ハイキングコースなど自然環境豊かなこの地では、サントリー山崎蒸溜所があることからウイスキーの生産で有名です。山崎は有名な企業や名所が狭い場所に集結している珍しい場所でもあるのです。ここでは「聴竹居」以外にもぜひ訪れて欲しい大山崎周辺の観光スポットをご紹介します!
サントリー山崎蒸溜所

http://blog.livedoor.jp/bzp17576/archives/52009230.html
1923年サントリーの創業者、鳥井信治郎が建設した「サントリー山崎蒸溜所」日本初のモルトウイスキー蒸溜所としても知られています。
初代工場長は大人気を博した朝ドラ「マッサン」のモデルとなった竹鶴政孝です。山崎は離宮の水と言われる名水が豊富に沸く場所であることから、ミネラルバランスの良い軟水として最高の水質を誇ります。その名水から作られた日本人に愛されるウイスキーの味を現代になっても守り続けています。
工場は無料で見学可能!(一部有料もあり)土日祝の午後はガイドセミナーはコースによって料金が発生します。事前に予約が必要なのでご注意を。
■ 基本情報
- ・名称: サントリー山崎蒸溜所
- ・住所: 大阪府三島郡島本町山崎5-2-1
- ・アクセス: JR山崎駅、阪急大山崎駅から徒歩約10分
- ・営業時間:9:00~17:00
- ・定休日: 年末年始・工場休業日(臨時休業あり)
- ・電話番号: 075-962-1423(受付時間:休業日をのぞく9:30~17:00)
- ・料金: 山崎蒸溜所ガイドツアー(無料)セミナープログラム(有料) 1,000円〜
- ・公式サイトURL: http://www.suntory.co.jp/factory/yamazaki/
アサヒビール大山崎山荘美術館

https://www.youtube.com/watch?v=6t5pJo-L8Fw
大正から昭和初期にかけて加賀正太郎によって建築された「大山崎山荘」(登録有形文化財)が元になった美術館「アサヒビール大山崎山荘美術館」
1995年には建築家・安藤忠雄設計によって地中館、2012年の竣工の山手館が新たに加えられました。民藝運動の参加した作家の陶磁器を中心に、漆器、染色、織物、日本画、西洋絵画、現代彫刻などで構成される約1000点を所蔵し、100点程度を常設しています。
■ 基本情報
- ・名称: アサヒビール大山崎山荘美術館
- ・住所: 京都府乙訓郡大山崎町大山崎銭原5−3
- ・アクセス:JR山崎駅、阪急大山崎駅から徒歩約10分
- ・営業時間: 10:00~17:00
- ・定休日: 月曜日、年末年始・臨時休業あり
- ・電話番号: 075-957-3123(総合案内)
- ・料金: 一般:900円(団体:800円)高・大学生:500円(団体:400円)
- 障害者手帳をお持ちの方:300円 小・中学生:無料
- ・公式サイトURL:
妙喜庵

http://blog.livedoor.jp/aijyu/archives/52250880.html
京都府乙訓郡大山崎町にある仏教寺院「妙喜庵」山号は豊興山。別名妙喜禅庵とも呼ばれています。連歌の祖である山崎宗鑑が住んでいたとの説もある寺院です。
見どころは国宝の茶室「待庵(たいあん)」。日本最古の茶室建造物であると同時に、千利休が作ったとされる唯一現存している茶室です。見学にはおよそ1か月前までに往復はがきによる予約が必要なので早めの準備が大切です。
■ 基本情報
- ・名称: 妙喜庵
- ・住所: 京都府乙訓郡大山崎町竜光56
- ・アクセス:阪急大山崎駅から5分
- ・拝観: 1ヶ月以上前に往復はがきで複数の日を記載してお申し込み
- ・定休日: 月曜日と水曜日(12月20日以降翌年1月15日くらいまで)
- ・電話番号: 075-956-0103
- ・料金: 無料
- ・公式サイトURL: http://www.eonet.ne.jp/~myoukian-no2/
離宮八幡宮

http://blog.livedoor.jp/toujiin/archives/548548.html
阪急大山崎からなら、西国街道に沿って西へ100メートルほどのところにある「離宮八幡宮」東門(大山崎町指定文化財)が目印です。
「離宮八幡宮」は、石清水八幡宮の元社にあたり、八幡大神を祭神とする神社として知られています。清和天皇の勅命により「石清水八幡宮」が建立されたのが前身とされています。その後、嵯峨天皇の離宮「河陽(かや)離宮」跡であったので社名を現在の「離宮八幡宮」に改めました。
■ 基本情報
- ・名称: 離宮八幡宮
- ・住所: 京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷21-1
- ・アクセス: 阪急京都線大山崎駅から徒歩3分
- ・電話番号: 075‐956‐0218
- ・料金: 無料
- ・公式サイトURL: http://rikyuhachiman.org/
霊泉連歌講跡碑

http://lapizlazuri.net/ooyamazaki.html
天王山登山口に建つ「霊泉連歌講跡碑」そばには山崎宗鑑句碑もあります。山崎宗鑑は、室町幕府9代将軍足利義尚に仕える武士でした。義尚の陣没(延徳元年、1489年)後に出家し大山崎に隠棲してからは、連歌講の中心人物になり、俳句の指導などを精力的に行っていたとされています。
晩年は『新撰犬筑波集』などを発表し、俳諧の創始者として知られ、霊泉連歌講跡碑の横にある山崎宗鑑句碑の句には、ホトトギスにまつわる句が彫られています。
■ 基本情報
- ・名称: 霊泉連歌講跡碑
- ・住所: 京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷21-1
- ・アクセス:阪急京都線「大山崎駅」から徒歩8分
大山崎町歴史資料館

大山崎の文化と歴史について詳しく知りたい方におすすめなのが「大山崎町歴史資料館」大山崎ふるさとセンターの中の2階にある施設です。
施設内は古代コーナー、中世コーナー、そして山崎合戦と待庵・利休のコーナー、近世コーナーという4つのコーナーで構成されていて、これまで大山崎が歩んできた歴史的特色を分かり易く、展示・解説しています。
■ 基本情報
- ・名称: 大山崎町歴史資料館
- ・住所: 京都府乙訓郡大山崎町大山崎竜光3番地 大山崎ふるさとセンター2階
- ・アクセス:JR山崎駅から徒歩6分
- ・営業時間: 9:30~17:00
- ・定休日: 毎週月曜日(但し祝日の場合は翌日) 祝日の翌日(臨時休館あり)
- ・電話番号: 075-952-6288
- ・料金: 大人 200円 小・中学生 無料 大人団体割引あり
- ・公式サイトURL: http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/soshiki_view.php?so_cd1=40&so_cd2=135&so_cd3=…
京都・大山崎の穴場観光スポット「聴竹居」特集いかがでしたでしょうか?昨年(2014)11月には「紅葉をめでる会」(建物内部の有料公開と庭園無料公開)が開催されました。通常は予約制ですがこの日は予約なしに入れます。今年はまだ未定ですがぜひHPなどで確認してください♪
素材提供:トリップアドバイザー