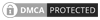http://www.rodneywilson.ca/tag/indian-music/
インド音楽は他の国とは全く違う独自の旋律が特徴。一度を聴くとその独特な世界に引き込まれてしまう不思議な世界観があります。インドへ旅行に出かけたことのある人はもちろん、出かけたことがない人も、初心者がインドの音楽を聴くための基礎知識をまとめました。 1. インド音楽とは?

http://www.kalikrama.com/2014_04_01_archive.html
インドの伝統音楽を大別すると北部を中心とした「ヒンドゥスターニー音楽」と南半島を中心とする「カルナータカ音楽」に分けられます。ただ多民族国家であるため、地域や人種によって音楽もまちまちでジャンルを分けるのは至難の業。そこで手軽に誰でもわかるインド音楽の聴き方を知っておきましょう。 インド伝統音楽の特長その1 「歌が主体」

http://en.wikipedia.org/wiki/Kaushiki_Chakrabarty
インド音楽は基本は声による歌が主体。器楽演奏もありますが、あくまでも声のパートをなぞるとか、伴奏するためのもの。また、インドには合唱はありません。つまり、ハーモニーはなく、あくまでもメロディラインを独唱したり、斉唱したりするのがインド音楽の特長です。 インド伝統音楽の特長その2 「リズムは輪廻転生」

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_India
インド音楽のリズムはあるリズムパターンの繰り返しとなっていて、周期性をもってパターンは繰り返されます。このときにどんな曲も最初のリズムパターンで終了するという仕組みになっています。これは死は生の始まりというヒンドゥー教の輪廻の思想に似ています。 インド伝統音楽の特長その3 「西洋文化の影響がほとんど見られない」

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_India
200年以上イギリスの植民地だったインドですが、音楽が影響を受けることはありませんでした。インドの伝統音楽は西洋音楽とはかけ離れています。バイオリンは伝統楽器のように演奏することはありますが、ピアノで伴奏したり、西洋の音楽が出てくることはまずありません。 http://kitchen-pharmacy.blogspot.jp/2012/01/in.html
また音楽の構造が即興主体であることもクラシックな西洋音楽とは違います。まるでジャズのように即興を繰り返していきます。因みにインドの学校では音楽の授業はインドの音楽を勉強し、日本のように西洋音楽を学校で学ぶことはないのだそうです。 2.インド音楽で使われる楽器

http://foodieandthebeast.org/
インド音楽で使用される楽器にはどのようなものがあるのでしょうか。また、それぞれどんな音色がするのでしょうか?歌が主体とはいえ、インド音楽では独特な楽器の音色が重要な役割を果たしています。 シタール(Sitar)
.jpg)
http://spicmacay.apnimaati.com/2012/12/sitar-maestro-pandit-prateek-chaudhuri.ht….
インド音楽で一番有名な楽器でしょう。リュートの一種で全長は約120cm、重さは約2.5kgあります。棹に弧状の金属製フレットが糸で固定されていますが、ラーガ(音階)に応じて動かせるようになっています。 独特な持続音は、この共鳴弦とコマの構造によるもので、弦が振動するとそのコマに触れて弦が細かく響くのです。三味線や琵琶の「さわり」と同じ構造といえます。
ヴィーナ(Veena)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_image_of_Veena.JPG
直径約50cmの空洞の木か瓢箪の台座2つを,約70cmの竿で繋いだ形の弦楽器。竿に7本の弦が張ってあり,棹の上には金属製のフレットがついています。フレットは南インドのヴィーナは24個,北インドのヴィーナは20~26個で、北はヒンドゥスターニー音楽、南はカルナータカ音楽に使われます。 弦をピックで弾くことにより音を出します。キレイな音色です!
タンブーラ(Tambura)

http://en.wikipedia.org/wiki/Tanpura
タンブーラーは決して主役ではなく縁の下の力持ち的な役割を果たす楽器です。コンサートの際、主奏者は、タンブーラーの音を聞きながら自分の楽器の調弦を慎重に行います。 演奏会では奏者の名前も紹介されず、難しい技術は不要だといわれている楽器ですが、常にドローン(通奏低音)を奏でていて主奏者とは別に最初から最後まで基準音を鳴り響かせている重要な役割を果たします。独特の響きがある楽器です
サロード(Sarod)

http://antiquitymusic.com/store/index.php?route=product/product&product_id=356
ヒンドゥスターニー音楽で使われる弦楽器では、シタールと並んでポピュラーな楽器です。フレットがないので演奏には奏者の音感が重要。スチール製の弦は25本あり、旋律演奏用、ドローン用、共鳴用など用途が分かれています。ピックはココナツの殻でできています。(象牙製もあります) サーランギ(Sarangi)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghualam_Ali_Sarangi_Solo_In_Evening_Raga_….
ヒンドゥースターニー音楽で重要な役割を果たす擦弦楽器(弓で弦を擦る楽器)です。バイオリンのように指の腹で弦を押さえず爪側で押さえて音を出します。弦は40本近くあります。 サーランギはインド古典歌謡の声を模倣して演奏されます。声と同じように表現することから歌の知識のある人が演奏します。
サントゥール(Santur)

http://jyounetu-activities.seesaa.net/article/155322787.html
3オクターブの音域がある打弦楽器(張っている弦を叩いて音を出す楽器)。軽い木の撥を使って鋼鉄製の弦を叩くと乾いた音がします。ペルシャ音楽でもお馴染みの音です。 アイルランドのダルシマー、中国の揚琴、韓国のヤングム、モンゴルのヨーチンも同じ仲間の楽器です。
ハーモニウム(Harmonium)

http://batish.com/catalog/inst/Harmonium/
もともとはリードオルガンと呼ばれるリードを用いたオルガンとして西洋で生まれたものですが、インドがイギリスの統治下に入ってからインド独自に開発され、座って演奏するのではなく膝の上に乗せて演奏するスタイルとなり、インド音楽に欠かせない楽器となりました。 インド音楽ではハルモニウムは歌の伴奏で用いられることが多くあります。
タブラ(Tabla)

http://www.gharanaarts.com/glossary-of-the-instruments/
インド音楽の中で最も人気が高いのがタブラと呼ばれるこの打楽器。音色や複雑なテクニックに魅了されている人も多いのではないでしょうか。タブラは2個で1対です。ダーヤン、バーヤンと呼ばれ左右が決まっていて、音程も違います。 パカワージ(Pakhawaj)
.jpg)
http://www.dhrupad.info/dalchandsharma.htm
日本の締太鼓のように紐の張力で音程を調整する打楽器です。タブラが生まれる元になった楽器で、叩き方や叩く位置によって音程や音色が変わってきます。 シャハナーイ(Shehnai)

http://194.250.166.236/creparth/instruments-musique/instrument/shehnai.htm
北インドでポピュラーなリード楽器。ダブルリードでオーボエのように演奏します。チャルメラのような音が出ます。 バーンスリー(Bansuri)

http://tablamontreal.blogspot.jp/2011/01/catherine-potter-canadian-pioneer-of.ht….
インドの竹製のフルートです。大変歴史の古い楽器でインドの古典叙事詩「マハーバーラタ」にも登場します。もともと作曲されたメロディがあるのではなく即興でメロディを紡いでいきます。 3. インド古典音楽の有名人
ラヴィ・シャンカール (Ravi Shankar)
/Pandit%20Ravi%20Shankar/pandit-ravi-shankar-0a.jpg)
http://www.santabanta.com/wallpapers/pandit-ravi-shankar/
シタールの名人であり作曲家。1920年生まれ1912年没。ビートルズに影響を与えた人物として有名です。シタール奏者のアヌーシュカ・シャンカル、ジャズ歌手のノラ・ジョーンズのお父さんでもあります。ポピュラーや西洋楽器、また日本の邦楽器ともコラボレーションするなど多彩な活動で知られます。 娘であるアヌーシュカと行なったライブ演奏です。
アムジャッド・アリ・カーン(Amjad Ali Khan)

http://preparedguitar.blogspot.jp/2014/05/amjad-ali-khan.html
1945年生まれ。サロードの巨匠と呼ばれています。伝統を継承しながら新たなサロードの楽器としての可能性を追求、世界中から賞賛を受けています。サロード奏者のトップといえば誰もがアムジャッド・アリ・カーンの名前をあげることでしょう。 アムジャッド・アリ・カーンの演奏です。
ザキール・フセイン(Ustad Zakir Hussain)

http://momentrecords.com/media.html
1951年生まれムンバイ出身のタブラ奏者。ヒンドゥ・スターニー音楽を主体としていますが、海外の多くのミュージシャンとコラボレーションしており、世界中で最も評価の高いタブラ奏者の一人です。 もともとラヴィ・シャンカールのサポートをしていたことからニューヨークなどを頻繁に訪れ、ロックミュージシャンなどと競演するようになった経緯があります。
動画の超絶技巧をご覧ください! 演奏技術の高さにびっくりです。
シヴクマール・シャルマ(Shivkumar Sharma)

http://bobbakerfish.wordpress.com/2012/04/25/fragmented-frequencies-womadelaide-….
1938年生まれのサントゥール奏者。天才的な才能を持っていた彼はカシミール地方生まれのサントゥールに独特な改良を加え、彼ならではの音を追求してきました。即興が織り成す繊細な音の世界は大変個性的です。 1988年の来日コンサートでの演奏です。
4.日本でインド音楽を楽しみたい!

http://indianclassicstokyo.blogspot.jp/
少ないですが日本でもインド音楽のプロの日本人演奏家や舞踏家がいます。各地で頻繁にコンサートを行なっていますので、インド音楽を鑑賞してみてはいかがでしょうか。不定期にライブを行なっていますのでウェブサイトで情報をチェックして出かけてみましょう。 - バーンスリー奏者 寺原太郎さん
- バーンスリー奏者中川博志さん
- タブラ奏者U-zaan さん
- タブラ奏者森山繁さん
- シタール奏者武藤景介さん
- シタール奏者加藤貞寿さん
- シタール奏者田中峰彦さん
- サーランギ奏者小林祐介さん
- 野火杏子さん主催インド舞踊バラタナティアムスクール「コンテンポラリーナティアムカンパニー」
- 大東文化大学国際文化学科井上貴子教授研究室(インド音楽に関する出版物が紹介されています。教授自身もインド歌謡の歌い手です。)
- 東京音楽大学付属民族音楽研究所(不定期にインドの楽器についての公開講座が行なわれています)