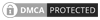熊野詣で有名な聖地、熊野。熊野本宮大社はじめ熊野三山はあまりにも有名ですが、熊野本宮大社から500メートルくらいのところにある、「大斎原」には行ったことはありますか?熊野本宮よりも素晴らしいとまで言われるパワースポット「大斎原」の魅力に迫ります!
熊野詣で有名な聖地、熊野。熊野本宮大社はじめ熊野三山はあまりにも有名ですが、熊野本宮大社から500メートルくらいのところにある、「大斎原」には行ったことはありますか?熊野本宮よりも素晴らしいとまで言われるパワースポット「大斎原」の魅力に迫ります!熊野本宮大社 旧社地「大斎原」とは?
大斎原(おおゆのはら)は、元々、熊野本宮大社があった地です。大斎原は、熊野川・音無川・岩田川が合流する中洲に位置し、中洲への橋がかけられるまでは、人々は歩いて川を渡ったため、川の水で水垢離(みずごり)を行い身を清めての参拝となったそうです。
大斎原にはかつて、上四社、中四社、下四社の計十二の社殿がありました。ところが、明治22年(1889年)の8月、大水害により、中四社、下四社が流出しました。
そのため、水害を免れた上四社が、現在の熊野本宮大社のある場所へと遷座しました。そして、大斎原には、流失した八社をまつる石造の小祠が建てられたのです。
熊野本宮大社 旧社地「大斎原」の魅力
日本書紀にもその名が登場する熊野の地は、古の神々にも縁の地で、「熊野の神々は、中州のイチイの巨木の梢に、三体の月の姿で降臨した」という言い伝えもあります。古来より聖地とされ、人々の信仰を集めてきたこの地は、不思議なエネルギーに満ちているらしく、近年は人気高いパワースポットとして、多くの人が訪れています。聖地「大斎原」の最大の魅力は、やはり古よりこの地に満ちる「気」に触れることでしょう。
熊野本宮大社 旧社地「大斎原」の見どころ
大鳥居
入り口に立つ大鳥居は、高さ約34m、幅約42mという大きさ。天に向かってそびえたち、雲にも届きそうなその大鳥居は圧巻です。その背後に広がる、こんもりと緑の茂る森が大斎原なのですが、入り口の鳥居だけで既に圧倒されてしまいそうです。豊かな森
祠
かつてこの地に建っていた、中四社、下四社をまつる祠が、ひっそりと佇んでいます。火の神や土の神、水の神らが祀られています。太古の昔より祀られてきた神々の祠だけあって、ここに一番強いエネルギーを感じる人もいるようです。来訪者の声
http://www.jalan.net/kankou/spt_30206af2172042874/kuchikomi/?screenId=OUW3701
お社など何もありませんが、今も残る参道の杉並木はとてもパワフルです。
方々は旧社とかふるみやなどと言うみたいです。日本一の鳥居と世界遺産登録を記した石碑、そして本宮のあった場所には石祠が2基建てられ、そこに本宮の第 五殿から第十二殿と摂末社が祀られているのみの広い野原の様になっており、古の鎮座しておられた雰囲気のみ感ずる事ができます。神域としてのパワースポッ ト振りは現在の本宮以上かもです。ここへ来るとトンビ達が雄壮に上空を飛び回りお詣りに来た人々を迎えてくれます。
http://www.jalan.net/kankou/spt_30206af2172042874/kuchikomi/?screenId=OUW3701
■ 基本情報
- ・名称:熊野本宮大社 旧社地「大斎原」
- ・住所:和歌山県田辺市本宮町本宮1
- ・アクセス:熊野本宮大社まで
- ワイドビュー南紀新宮駅から熊野交通・奈良交通本宮大社方面で約90分
- くろしお紀伊田辺駅から明光バス・龍神バス本宮大社方面で約120分
- ・電話番号:0735-42-0735(熊野本宮観光協会)
- ・公式サイトURL:http://www.hongu.jp/
素材提供:トリップアドバイザー