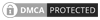勝龍寺城で細川忠興と、明智光秀の娘の玉(細川ガラシャ)が結婚式を挙げ、新婚生活をおくった場所として有名な場所ですが、その敷地内に、空海が開基した小さなお寺があることはご存知ですか?それが勝龍寺です。
勝龍寺城で細川忠興と、明智光秀の娘の玉(細川ガラシャ)が結婚式を挙げ、新婚生活をおくった場所として有名な場所ですが、その敷地内に、空海が開基した小さなお寺があることはご存知ですか?それが勝龍寺です。勝龍寺とは?
大干ばつ大飢餓の年、天皇が心を痛め、住職の千観上人に7日間の雨乞い祈祷を命じ、雨が降ったそうです。龍神に勝ったということから、青龍寺から「勝龍寺」に改名されました。本尊は鎌倉時代につくられた木造の十一面観音で、国の重要文化財に指定されています。
勝龍寺の魅力
びんずる尊者の像が安置され、病気の人がこのお像をなでた手で自分の悪い所をさすると、病気が治ると信仰されています。平成18年には、「ぼけ封じ観音」が安置されました。空海の頃は、観音堂を始め九十九坊が建てられていたと言われ、大きなお寺だったことが伺えますが、現在は住宅街に囲まれた、本堂と鐘楼があるだけの小さいお寺です。見どころ・オススメポイント
勝龍寺城
足利尊氏の命により、細川頼春によって1339年に築城されました。細川忠興と細川ガラシャが新婚時代を過ごした場所です。もともと空海が開基した勝龍寺があり、その場所も縄張りに含めてお城を建てたことから、名前もそのまま使って勝龍寺城になったそうです。織田信長と三好三人衆の「勝龍寺城の戦い」、天王山の戦い(山崎の戦い)で明智光秀軍と羽柴秀吉軍の戦いの舞台になった場所でもあります。勝龍寺公園
ガラシャおもかげの水
勝龍寺公園内に、「ガラシャおもかげの水」という石碑があります。細川ガラシャがこのあたりで細川忠興と新婚生活を過ごしていたことから、歴史のロマンにちなんで名付けられたそうです。その水道の水は地下水100%で、ペットボトルに汲んで帰る観光客もたくさんいます。。その向かい側にはガラシャと細川忠興の像が並んでいます。口コミ
http://www.ekiten.jp/shop_4872653/review/
http://kojodan.jp/castle/135/
■ 基本情報
- ・名称:勝龍寺
- ・住所:京都府長岡京市勝龍寺19−25
- ・アクセス:JR京都線 長岡京駅から徒歩10分
- ・電話番号:075−951−6906
- ・入館料:無料
- ・拝観時間:自由
- ・駐車場:なし
- ・その他:トイレなし